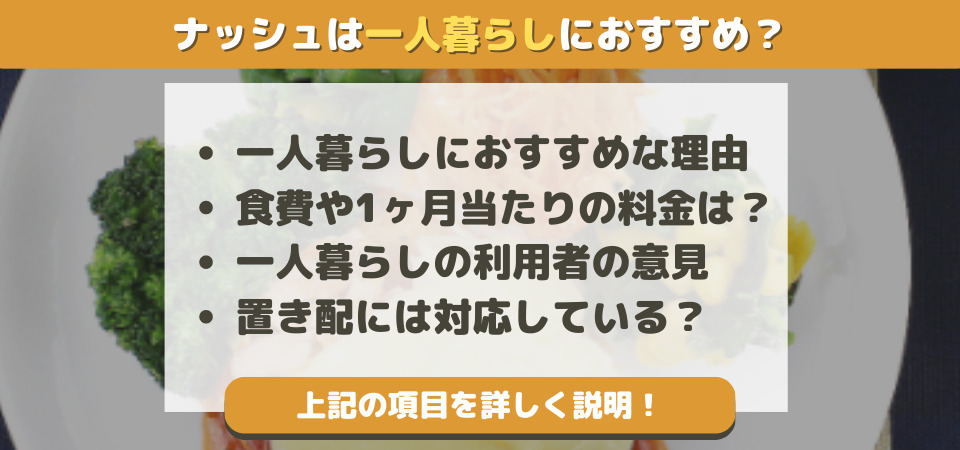
nosh(ナッシュ)は一人暮らしにおすすめ?コスパは悪い?自炊とどっちを選ぶべき?
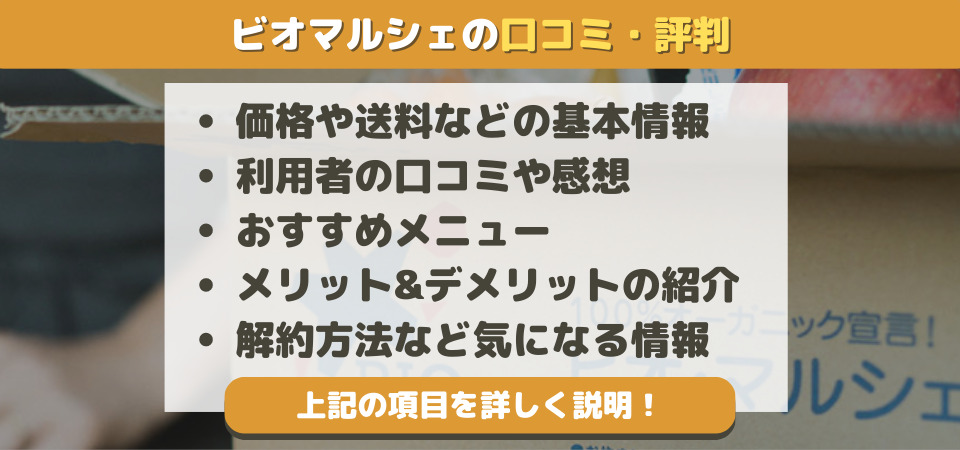
ビオマルシェの口コミ・評判・評価を紹介!お試しの内容は?値段が高いって本当?
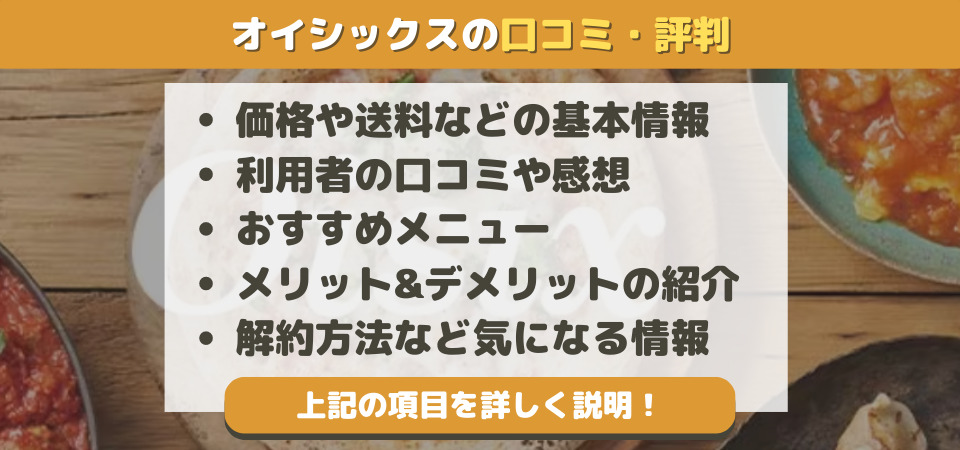
オイシックスの口コミ・評判・評価を紹介!ひどい・料金が高いという噂は本当?
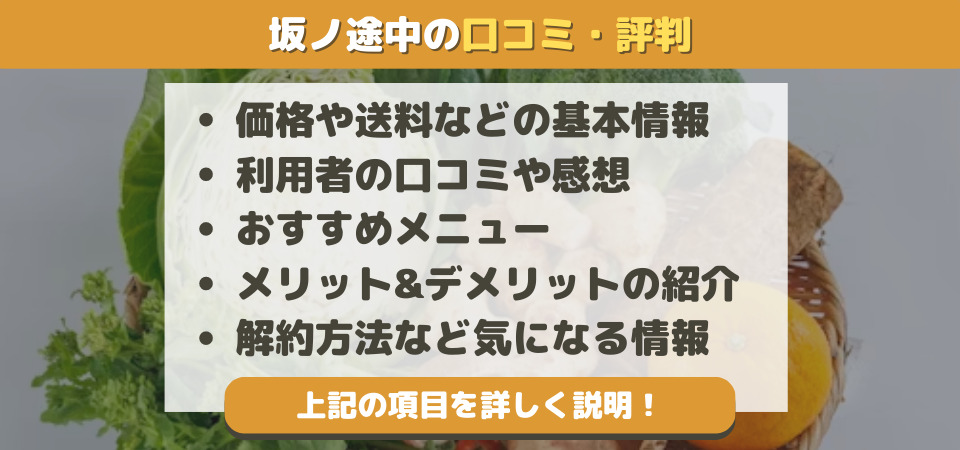
坂ノ途中の口コミ・評判・評価を紹介!お試し野菜セットの内容は?送料や退会方法も解説
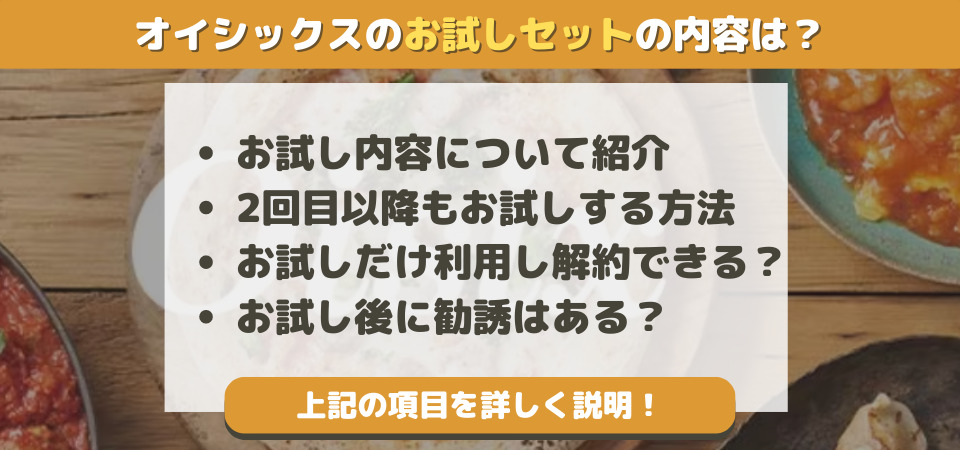
オイシックスのお試しセットの内容は?2回目以降も利用できる?初回のみ利用して解約可能?
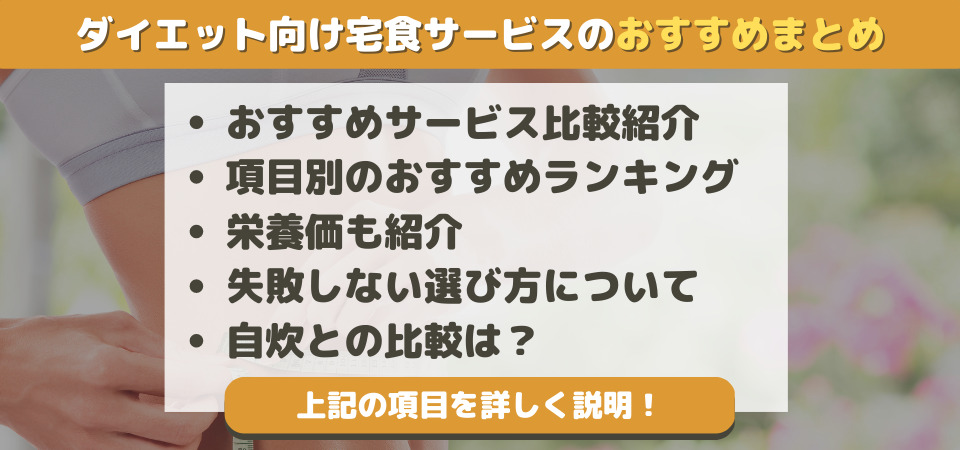
ダイエット向け宅食サービスのおすすめ7選 安いサービスや糖質制限・カロリー制限に優れたサービスはどれ?
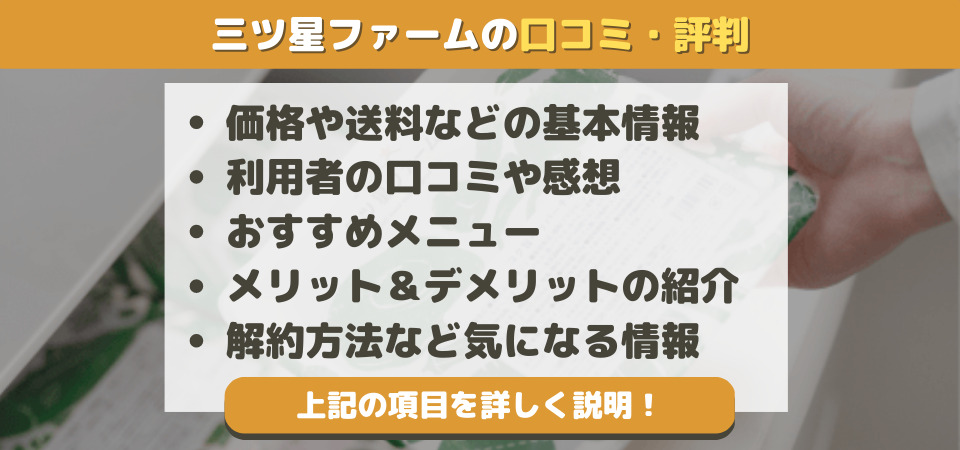
三ツ星ファームの口コミ・評判・評価を紹介!おすすめメニューやお試し内容についても徹底解説!
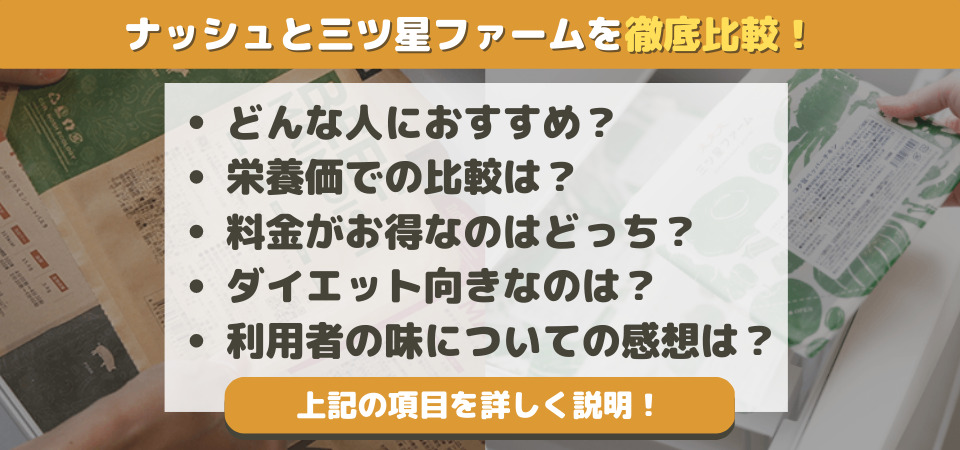
ナッシュと三ツ星ファームを徹底比較!料金・栄養価・味はどう違う?おすすめできる人は?
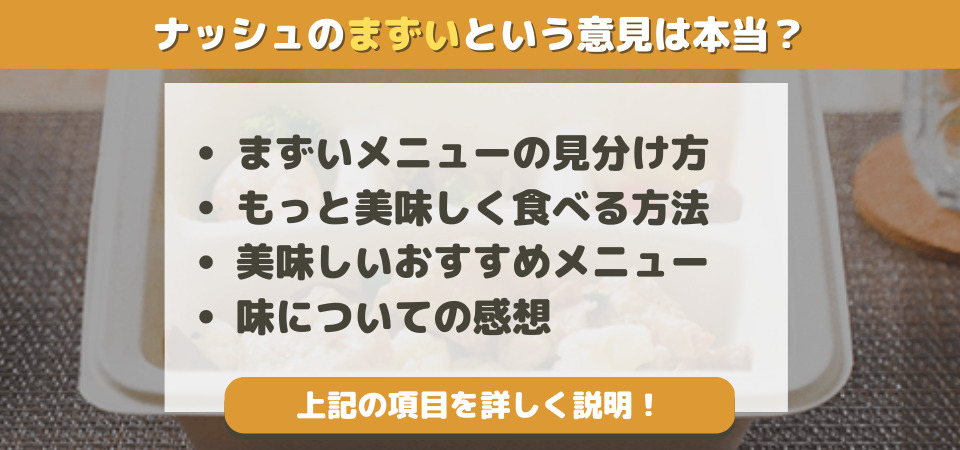
nosh(ナッシュ)が「まずい」と言われる理由は?美味しく食べるための解決策について徹底解説!
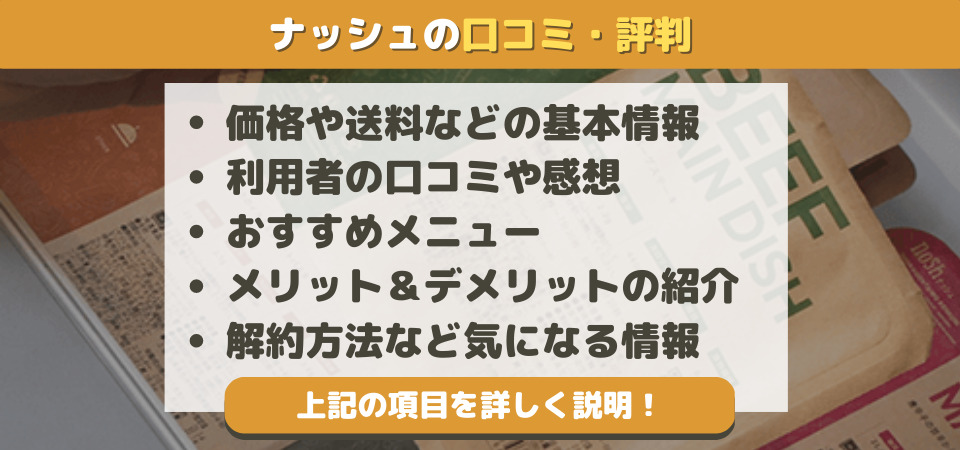
nosh(ナッシュ)の口コミ・評判・評価を紹介!一人暮らしにもおすすめ?1ヶ月の値段はいくら?
1